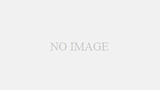昨今の少子高齢化がすごいことになっております。人口増加が右肩下がりを続けており1年間の出生数は70万人を割る見込み、合計特殊出生数は人口維持に必要な2.07を大幅に下回り1.3を割る状況となっております。
日本では婚姻数が少子化と密接に関わっていますが、今回は結婚という制度の問題点、また3組に1組といわれる離婚をした時についてどの様なことが起こるか見ていきましょう。
結婚はもう古い?現代において結婚がどんどん減っている理由
それではまず結婚についてです。昭和までの価値観では大人になって働き、結婚をして子供を作るというのは非常に当たり前の状況が続いていました。それは経済的理由、家事や世間体など総合的に結婚するのが当たり前という価値観があったからです。
今結婚自体が減っているのはどうしてでしょう。
非正規雇用の増加、物価高騰、女性の社会進出など従来の男性が稼ぎ女性が家のことをやるような経済の安心感が低下したことはひとつの要因でしょう。子供の教育などの費用が担保できない、女性も働きに出ないといけない社会となりました。
また男性側からすると結婚のメリットが減ったというのも一因でしょう。それは洗濯機や掃除機などの家電の進化、コンビニやアマゾンなどの生活が便利になり日中仕事で家を空けていても、家事がまかなえるようになってしまいました。皮肉なことに社会が便利になったことで一人で生活が楽になり結婚の必要性が相対的に減りました。
また結婚をしないという選択肢を尊重する、多様な価値観を受け入れる社会となったことも原因です。適齢期が近づき結婚を催促する様なことが悪とされ、本人も周りも結婚しないことを受け入れたことも要因でしょう。
結婚の晩婚化、30歳を超えて婚活を始めて、なんとか結婚しても高齢となっているため妊活が必要となるケースも多いです。若くして子供がたくさんいる社会を作りたいといいつつ、いざその様なことに陥ると生活苦となるケースも多いです。賢い人ほど結婚を避けたり、遅くする傾向もあります。
離婚をした時の性別格差
いざ結婚をして、子供ができても離婚をする夫婦もいます。女性が経済力をもったこと、男女格差が少なくなっとことも離婚をしやすくなっているようです。
結婚している時、財産の受け渡しは生活費を除くと贈与税の対象となります。NISAなど資産運用をするからと年間110万円を超える受け渡しは課税対象となります。夫婦といっても共有財産とはみなされない様です。
しかし離婚をする時は”なぜか”話が違う様です。財産分与という形で財産の半分を分け与えることもあります。もちろん片方の生活困窮を防ぐため、というのは理解できますが離婚事由によっては納得できないケースもありそうです。
親権も基本的に女性が有利です。このような離婚時のデメリットも賢明な男性から結婚を躊躇させる一要因になっているかもしれません。
結婚の制度はいい加減、そろそろ見直しの必要もありそうですね。結婚をせず事実婚で子供をつくる、もしくは一夫多妻など現代の実情に沿った制度を一考する時期が来たのかもしれません。
本日の記事は以上です。
次の記事もブックマークをしてお待ちください。
それではまたお会いしましょう、ばいばい!